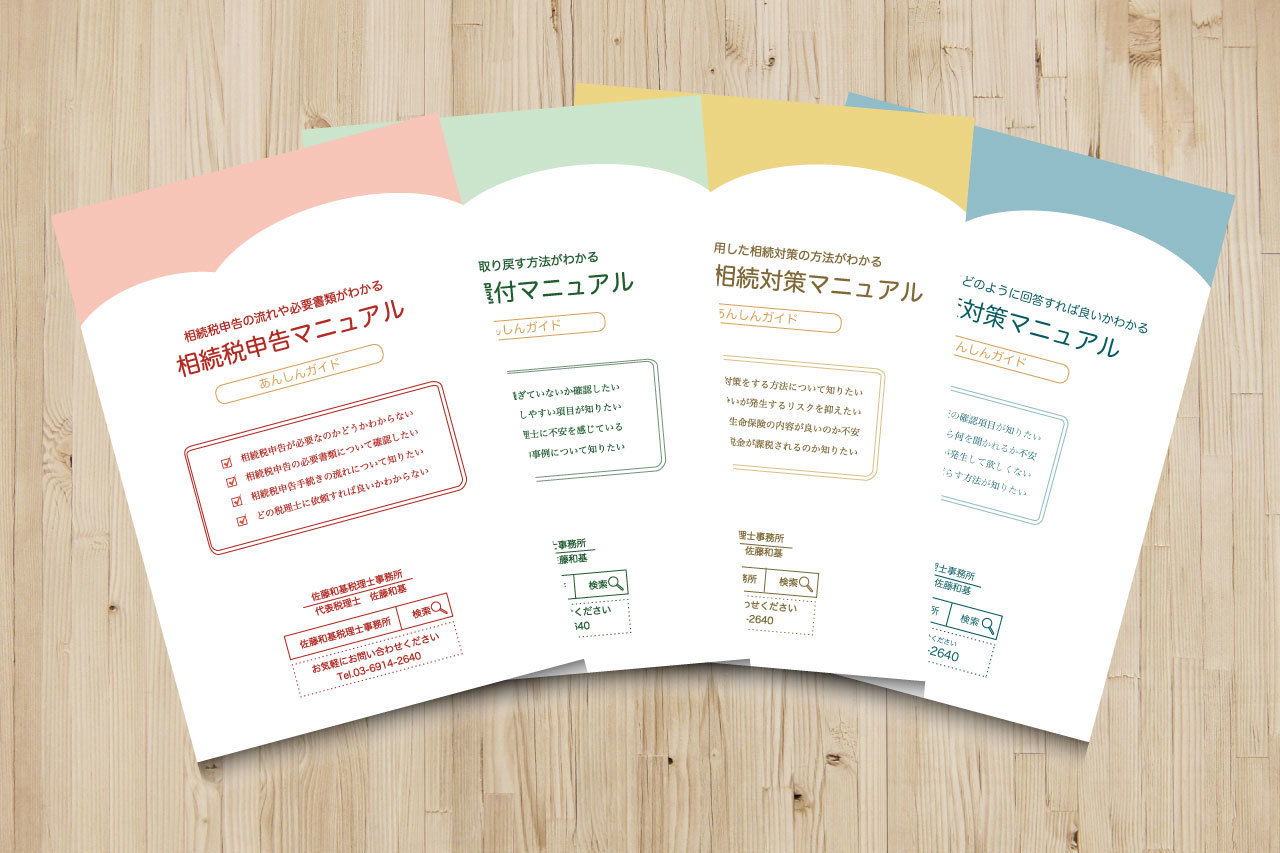相続土地国庫帰属制度の要件|いらない土地を手放す方法を解説
親から土地を相続したものの、「使い道がない」「固定資産税だけがかかる」「売れない」といった理由で、相続した土地の扱いに困っている方は少なくありません。
特に、山林や原野、田畑、地方の空き地などは、維持費ばかりがかかる「負動産」となり、子や孫など下の世代に負担を残してしまう恐れもあります。
こうした状況を受けて令和5年4月27日からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、一定の要件を満たす不要な土地を国に引き取ってもらえる制度で、手放したい土地を処分できる数少ない方法の一つです。
こちらのページでは、相続土地国庫帰属制度について、以下のポイントをわかりやすく解説します。
・制度の概要と仕組み
・国に引き取ってもらうための条件
・申請から手放すまでの流れ
・必要な費用と注意点
・国に引き取ってもらえない場合の山林引き取りサービスの活用
相続したいらない土地の処分方法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈(相続人に対するものに限ります)によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度です。
これまで、相続によっていらない土地を取得しても「管理できない」「売れない」といった理由から、土地を放置するケースが増えていました。
結果として、以下のような問題が全国的に深刻化していました。
・管理されていない空き地や山林の増加
・境界トラブルや不法投棄の温床
・子や孫など下の世代への負担の先送り
・所有者不明土地の増加
以上のような土地の放置や管理不全による社会問題への対策として令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度が創設されました。
なお、この制度を利用できる対象者は相続又は遺贈(相続人に対するものに限ります)により土地を取得した人です。
そのため、相続等以外の方法(売買等)により自ら土地を取得した人や、法人は基本的にこの制度を利用することができません。
なお、相続又は遺贈により土地の共有持ち分を取得した共有者は、他の共有者全員と共同して申請することによって、この制度を活用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、「どんな土地でもOK」ではありません。
以下の①から⑩のいずれかに該当する土地は承認申請の却下又は不承認となります。
そのため、以下の10項目のいずれにも該当しない土地である必要があります。
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路など他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、複数のステップがあります。
手続きの流れとしては①申請前の確認・準備、②承認申請(申請書類の作成と提出)、③法務大臣による要件審査・承認、④負担金の納付、⑤国庫帰属(引き取り完了)となります。
以下、申請から国に引き取ってもらうまでの流れを詳しく解説します。
①申請前の確認・準備
まずは相続土地国庫帰属制度の要件を満たしているかどうか確認します。
適用できない土地の要件は上記2.国庫帰属制度を利用できる土地の要件とは?の10項目となりますので、まずはこの10項目に該当しないかどうかを確認します。
承認申請をする際には①承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面、②承認申請に係る土地とその土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真、③承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真は添付が必須になりますので、最低限、この3点は事前に用意をして要件を満たしているかどうか確認します。
他にも添付は任意の書面になりますが、固定資産税評価額証明書、承認申請土地の境界等に関する資料(過去に作成された図面等)も確認した方が良いでしょう。
ご自身で判断をすることが難しい場合には、法務局で相談をすることができます。
相談は事前予約制で、時間も1回30分以内となっているため、事前にある程度は書類も用意して確認する点を明確にしておいた方が良いと思います。
②承認申請(申請書類の作成と提出)
申請書類の準備ができましたら、承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に提出します。
書類は原則として所有者本人が作成しなければなりませんが、弁護士、司法書士、行政書士の3士業に承認申請書類の作成代行を依頼するとは可能です。
ただし、3士業に書類作成の代行は可能ですが、提出は所有者本人が行う必要があります。
提出方法は法務局の窓口に提出するか、郵送で提出することもできます。
また、申請する際に審査手数料を納付します。
審査手数料は土地1筆につき14,000円になります。
③法務大臣による要件審査・承認
承認申請書類を提出しましたら、法務大臣が承認申請に係る審査のため、職員にその事実を調査させます。
審査の結果、要件を満たしていた場合は、法務大臣から承認の通知と負担金の通知がされます。
審査には数か月から1年程度かかる場合があります。
④負担金の納付
承認申請者は、承認の通知と負担金の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付する必要があります。
30日以内に納付しない場合は、承認の効力が失われてしまうため注意が必要です。
負担金は原則20万円ですが、一定の市街地等の土地については土地の面積に応じて負担金の額を計算します。
⑤国庫帰属(引き取り完了)
負担金の納付が完了すると、土地の所有権が国に移り、手続きも終了となります。
相続土地国庫帰属制度の利用に係る費用について説明します。
大きく分けると審査手数料と負担金が発生します。
他には専門家に依頼する場合などは別途費用が発生します。
ここでは申請者が負担することになる具体的な費用について説明します。
①審査手数料
申請の際には土地1筆あたり14,000円の手数料が必要です。
複数の土地が隣接している場合でも、1か所ではなく1筆につき14,000円の手数料が発生すめため、筆数が多い場合には、審査手数料の負担も大きくなります。
なお、承認申請を途中で取り下げた場合や申請が却下された場合でも、手数料は返還されませんので注意が必要です。
②負担金
負担金については、地目や面積によって異なります。
原則として20万円ですが、草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地については土地の登記上の地積に応じて負担金の額を算定します。
③その他の関連費用
申請書類の作成を弁護士、司法書士、行政書士の3士業に依頼する場合には、専門家費用が発生します。
相続土地国庫帰属制度はまだ新しい制度で、専門家費用の相場もはっきりとしていませんが、10万円から50万円の間くらいになると思われます。
依頼する内容によっても大きく異なります。
例えば土地の現地の写真撮影等から全てを依頼する場合には専門家費用も高くなってしまいますが、所有者本人が現地の写真撮影等を行い、一部分を専門家に依頼する場合は専門家費用も安くなります。
あとは承認申請する土地の量にもよって異なると思います。
また、専門家費用以外にも例えば建物が建っている等で相続土地国庫帰属制度の要件を満たしていない場合には、要件を満たすために建物を解体する必要があります。
土地の境界が不明な場合も境界確認や測量が必要になるケースも考えられます。
相続土地国庫帰属制度は相続したいらない土地を手放すことができる画期的な制度ですが、いくつか注意点もあります。
相続土地国庫帰属制度の申請をする前に、以下のポイントを確認した方が良いでしょう。
①審査に時間がかかる
申請から承認までの審査期間は、数か月から1年程度かかります。
そのため、すぐに土地を手放せる制度ではありません。
時間がかかったあげく、手放せない可能性もあります。
②要件を満たさないと却下される
申請後に要件を満たしていないことが判明した場合、申請は却下されます。
また、審査手数料も返還されません。
そのため、申請前に要件を満たしているか十分に確認する必要があります。
③反対する共有者がいると申請できない
共有名義の土地については、共有者全員で申請する必要があります。
そのため、1人でも反対する共有者がいると、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
④売却や寄付、引き取りサービスとの比較
相続したいらない土地は「売れない」「寄付もできない」と思っていても、中には売れるケースや役所にダメ元で相談したところ、寄付を受け付けてもらえるというケースもあります。
可能性は高くないと思いますが、急ぎでない場合には、他の方法について可能性がないかチャレンジしても良いでしょう。
また、佐藤和基税理士事務所の山林引き取りサービスのような民間の引き取りサービスもあります。
中には詐欺まがいな会社もあるため、引き取りサービスを利用する場合には慎重に依頼する会社等を判断をする必要がありますが、相続土地国庫帰属制度が適用できないような土地でも容易に処分できるケースが多々あります。
佐藤和基税理士事務所の山林引き取りサービスについては、以下の記事で詳しく説明します。
山林引き取りサービスは佐藤和基税理士事務所が山林等を専門に扱う不動産会社や林業の会社等と提携して、不要な山林、原野、別荘地、宅地等を引き取るサービスです。
地目は山林に限らず、農地以外であれば、日本全国引き取り可能です。
農地については、農地転用(他の地目に変更)できる場合は引き取り可能です。
以下、山林引き取りサービスの具体的な内容について説明します。
申込ができる人
山林引き取りサービスは、民間のサービスとなりますので取得原因を問わずに申込可能です。
相続したいらない土地を手放したい方だけでなく、原野商法等で騙されて買ってしまった人や法人でもご利用いただけます。
また、申込も所有者本人に限らず、ご家族の方や相談を受けている士業、不動産会社、銀行等の代理でのお申込みも可能です。
申込先
山林引き取りサービスのお申込みは、お問合せフォームからお問合せください。
※佐藤和基税理士事務所及び一般社団法人相続財産再鑑定協会のどちらからお問合せいただいても対応可能です。
お問合せいただいた方にメール添付にて、申込書を添付しますので、申込書と必要書類(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送で提出していただく場合は、資料の返却を行っていません。
そのため、郵送の場合はコピーでの提出をお願いします。
引き取り費用のお見積りまでは数日から1ヵ月程度です。
※筆数が多すぎる場合や引き取るリスクが非常に高い場合は、1ヵ月を超える可能性もあります。
引き取り費用について
山林引き取りサービスの費用については、お見積りまでは無料となります。
相続土地国庫帰属制度の審査手数料のようなものは発生しません。
引き取り可能な場合の引き取り費用は物件によってケースバイケースです。
物件によっては無償引き取りできるケースもあります。
また、基本的には契約不適合責任も発生しない契約となります。
※極端にリスクが高い物件などイレギュラーなケースでは契約内容も個別相談で変わる可能性はあります。
引き取り費用について
基本的には地目を問わず、日本全国の土地を引き取り可能です。
ただし、農地については、農地転用(他の地目に変更)可能な場合の引き取りとなります。
引き取り後の活用事例
山林引き取りサービスをご利用いただく不動産は、売買や寄付ができずに手放せない物件となりますので、一般的には活用が困難であるケースが大半です。
そのため、引き取り後に長期保有となってしまうことが多いですが、活用できるケースでは下記のようなものがありました。
・キャンプ場やサバゲーとして利用
・別荘地として利用
・キノコの栽培目的で利用
・植木屋が植木を育てるために利用
・林業として利用
・猟師が狩猟目的で利用
・自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
・太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)
山林引き取りサービスの実績
山林引き取りサービスは令和元年7月から佐藤和基税理士事務所が開始したサービスで、令和7年7月末までの申込件数、成約件数、成約見込み(契約予定)件数の実績は以下の通りです。
・申込件数585件
・成約件数167件
・成約見込み(契約予定)件数11件
・その他検討中複数件
成約しなかった事例の理由としては以下のものがあります。
・農地で農地転用(他の地目に変更)ができなかった。
※農地法の関係で、農地のままでは基本的に引き取りができません。
・引取り費用が申込者の予算を超えていた。
・親族等が引き取った。
・役場が寄付を受け付けた。
・相見積もりで他に安く引き取ってもらえる業者がいた。
相続土地国庫帰属制度が利用できずにお困りの方は、佐藤和基税理士事務所にご相談ください。山林引き取りサービスは審査手数料等が発生しませんし、お見積りまでは無料となりますので、気軽にご相談できます。
なお、相続土地国庫帰属制度の利用と同時並行でのご相談も可能です。
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスのお客様の声
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
お客様の声①
「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
お客様の声②
「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
よくご質問いただく内容
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
Q2.引き取った山林をどうしているのですか?
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスのお問合せはこちら
非線引き区域の山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com